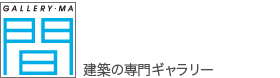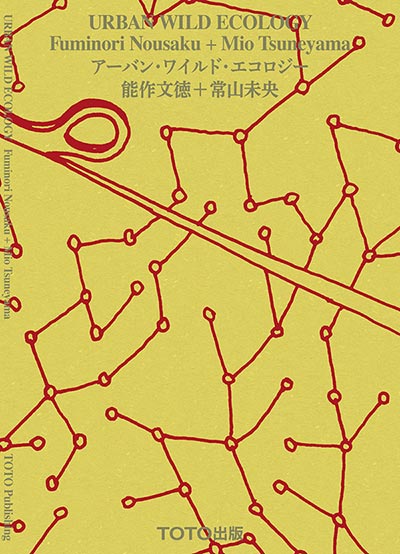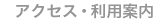- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

コラム
「建築のすそ野を広げたい」という想いで設立された編集事務所Office Bungaの磯達雄さんにご協力いただき、「能作文徳+常山未央展:都市菌(としきのこ)――複数種の網目としての建築」をより深く楽しむのに役立つ情報をお届けします。
今回は哲学者の篠原雅武さんをお招きし、人間と自然の関係性から、能作さん、常山さんが考える建築の射程についてお話いただきました。
今回は哲学者の篠原雅武さんをお招きし、人間と自然の関係性から、能作さん、常山さんが考える建築の射程についてお話いただきました。
能作文徳+常山未央展を楽しむためのコラム特別編 篠原雅武氏を迎えた鼎談
- 前編「人新世の建築はいかに可能か」
- 後編「ハビタブルな環境をつくるには」
人新世の建築はいかに可能か
能作:篠原さんとは、2016年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示で、制作委員としてご一緒させていただきました。そのときに私たちが出展する「不動前ハウス」や「高岡のゲストハウス」といった建物群を、「縁」という言葉で表現されました。
篠原:そうでしたね。
能作:あの頃、篠原さんは『生きられたニュータウン』(青土社)という、団地が衰退していく状況をどう考えていくかを論じられていました。私たちは改修の仕事が多く、古びた建物を人が暮らす場所として活用していました。あれから8年が経って、新築の仕事では、土中環境や生分解性材料に取り組むようになりました。建築ができるだけゴミにならない、土中や水脈に負荷をかけないようにしています。
常山:私たちは「西大井のあな」で継続的に自宅兼事務所の改修を行なっているのですが、そこでの実践が、別のプロジェクトに反映されたり、あるいは別のプロジェクトでの学びや問いが改修の試みにつながったりしています。新築か改修かで区別している意識はありませんが、使う材料や構法的なところから、建築を問い直しています。
篠原:今回の展覧会を見て、お二人が、手で触れることのできるレベルで水や土という事物と取り組んでいると感じました。私の場合、人為的に構築された世界のあり方と、その奥底に広がる「人間ならざる領域」との関係といったことに関する哲学的な考察にこだわっているのですが、つまり、手触りの世界からますます遠ざかって浮世離れした夢想的思考の世界の住人になったかと、反省しきりです。『生きられたニュータウン』を書いてみて、まだ思考が徹底できていなかったことの問題の一つが、人為の領域のリミットというか、その有限性と、それを超えたところにあるものをめぐる思考といったことです。ハンナ・アーレントは、『人間の条件』という著作で、人間を人間にするのは何かという問いを立て、それを条件づけるものをめぐる考察を展開しますが、人間の世界が自然の世界から切り離されるということが条件であると述べています。そのためにも、work(制作)という活動が大切で、それによりつくり出された人間の製造物により人間は条件づけられ、自然のプロセスから切り離されることによって、人間は存在できるようになると言っています。アーレント自身、自然のプロセスに人間の世界が浸食されてしまうことに、恐怖を感じていたのでしょう。人間世界の持続性、永続性といったことが、人間の存続を可能にする。そのためにも、自然をコントロールし、そこから切り離されることが要請されるし、人間世界がその切断において構築されることもまた要請される。
ところが、そう言っておきながら他方でアーレントは、人間が地球的な条件から切り離されうると考えること自体に無理があると考えています。すなわちアーレントは、次のように述べます。「地球は、人間の条件の本質そのものである。そして、地球という自然は、私たちすべてが知るように、人間存在に住み着くための場を提供するもので、その点で宇宙において独自と言えるが、というのも、そこで人間は、いかなる努力も人為的なものもなくして動き息することができるからだ」。これはジレンマですよね。アーレントは、このジレンマを、「切断の必然性」において解消してしまうのですが、アントロポセン(人新世)という状況(人為的活動が地球の在り方に影響を与えていくのにともなって地球の在り方が人間の予見、コントロールを超えてしまう)においては、アーレントの議論には限界があると考えられます。これは、チャクラバルティが『The Climate of History in a Planetary Age』で述べていることです。すなわち、人新世では、人間が切り離したと思ったはずの地球的条件によって、人間は脅かされてしまう。例えば地震などの自然災害や、地球温暖化という形で。
この状況において、自然と人間の調和をあらためて目指すといったことは、問題にならない。人為的構築物は、この都市化された世界においては、自明のものとなっているし、それを自然と調和させようにも、自然のほうが人間を超えているのだとしたら、むしろ調和的関係とは別の、謎めいたものと畏敬をもって関わり合うといったことが求められるでしょう。
今回の展覧会で見たもので言うと、例えば土の中に掘り込んでいくということ自体も人間による自然への介入の一つではないでしょうか。自然から切り離されていくのではなく、土中の微生物の力を借り受けて、それと一緒になって、伝統構法等も参照しつつ新たなテクノロジーを開発するとか、そういうことではないかと考えました。
篠原:そうでしたね。
能作:あの頃、篠原さんは『生きられたニュータウン』(青土社)という、団地が衰退していく状況をどう考えていくかを論じられていました。私たちは改修の仕事が多く、古びた建物を人が暮らす場所として活用していました。あれから8年が経って、新築の仕事では、土中環境や生分解性材料に取り組むようになりました。建築ができるだけゴミにならない、土中や水脈に負荷をかけないようにしています。
常山:私たちは「西大井のあな」で継続的に自宅兼事務所の改修を行なっているのですが、そこでの実践が、別のプロジェクトに反映されたり、あるいは別のプロジェクトでの学びや問いが改修の試みにつながったりしています。新築か改修かで区別している意識はありませんが、使う材料や構法的なところから、建築を問い直しています。
篠原:今回の展覧会を見て、お二人が、手で触れることのできるレベルで水や土という事物と取り組んでいると感じました。私の場合、人為的に構築された世界のあり方と、その奥底に広がる「人間ならざる領域」との関係といったことに関する哲学的な考察にこだわっているのですが、つまり、手触りの世界からますます遠ざかって浮世離れした夢想的思考の世界の住人になったかと、反省しきりです。『生きられたニュータウン』を書いてみて、まだ思考が徹底できていなかったことの問題の一つが、人為の領域のリミットというか、その有限性と、それを超えたところにあるものをめぐる思考といったことです。ハンナ・アーレントは、『人間の条件』という著作で、人間を人間にするのは何かという問いを立て、それを条件づけるものをめぐる考察を展開しますが、人間の世界が自然の世界から切り離されるということが条件であると述べています。そのためにも、work(制作)という活動が大切で、それによりつくり出された人間の製造物により人間は条件づけられ、自然のプロセスから切り離されることによって、人間は存在できるようになると言っています。アーレント自身、自然のプロセスに人間の世界が浸食されてしまうことに、恐怖を感じていたのでしょう。人間世界の持続性、永続性といったことが、人間の存続を可能にする。そのためにも、自然をコントロールし、そこから切り離されることが要請されるし、人間世界がその切断において構築されることもまた要請される。
ところが、そう言っておきながら他方でアーレントは、人間が地球的な条件から切り離されうると考えること自体に無理があると考えています。すなわちアーレントは、次のように述べます。「地球は、人間の条件の本質そのものである。そして、地球という自然は、私たちすべてが知るように、人間存在に住み着くための場を提供するもので、その点で宇宙において独自と言えるが、というのも、そこで人間は、いかなる努力も人為的なものもなくして動き息することができるからだ」。これはジレンマですよね。アーレントは、このジレンマを、「切断の必然性」において解消してしまうのですが、アントロポセン(人新世)という状況(人為的活動が地球の在り方に影響を与えていくのにともなって地球の在り方が人間の予見、コントロールを超えてしまう)においては、アーレントの議論には限界があると考えられます。これは、チャクラバルティが『The Climate of History in a Planetary Age』で述べていることです。すなわち、人新世では、人間が切り離したと思ったはずの地球的条件によって、人間は脅かされてしまう。例えば地震などの自然災害や、地球温暖化という形で。
この状況において、自然と人間の調和をあらためて目指すといったことは、問題にならない。人為的構築物は、この都市化された世界においては、自明のものとなっているし、それを自然と調和させようにも、自然のほうが人間を超えているのだとしたら、むしろ調和的関係とは別の、謎めいたものと畏敬をもって関わり合うといったことが求められるでしょう。
今回の展覧会で見たもので言うと、例えば土の中に掘り込んでいくということ自体も人間による自然への介入の一つではないでしょうか。自然から切り離されていくのではなく、土中の微生物の力を借り受けて、それと一緒になって、伝統構法等も参照しつつ新たなテクノロジーを開発するとか、そういうことではないかと考えました。

能作:この展覧会のコンセプト文に、「菌(きのこ)のような弱い力で現代都市を分解して再組織化する」と書きました。参考にしたのは、建築家のウィリアム・マクダナーと化学者のマイクル・ブラウンガートが書いた『サステイナブルなものづくり―ゆりかごからゆりかごへ(クレイドル・トゥ・クレイドル)』(人間と歴史社)という本です。その中に二つのサイクルの図があります。一つは人工物の循環で、もう一つは自然界のサイクル。その二つが混在して建築はできているけれども、それらが分離不可能な状態にするとリサイクルできないから分離可能にしましょうという考え方です。
その一方で、今、デザインの分野では、リジェネラティブ・デザインが注目されています。3R(Reduce, Reuse Recycle)という人工物の循環に加えて、自然界の循環に人間が介入して自然を再創造(Regenerative)する考え方です。ヨーロッパやアメリカではデザインの新しい潮流として捉えられています。ただ、これを極端に推し進めていくと人工的に雲を発生させて温暖化を防止することや、遺伝子レベルで自然に介入することも可能です。農作物に被害を与える害虫や、病気を伝染させる蚊が発生しないように、遺伝子を組み変えてしまう。実際に応用した例では蚊を減少させた結果、別の害虫が発生したということです。人間が自然を再創造することによって、またしっぺ返しが来る。危機的な状況を自分たちでつくってしまっているわけです。
その一方で、今、デザインの分野では、リジェネラティブ・デザインが注目されています。3R(Reduce, Reuse Recycle)という人工物の循環に加えて、自然界の循環に人間が介入して自然を再創造(Regenerative)する考え方です。ヨーロッパやアメリカではデザインの新しい潮流として捉えられています。ただ、これを極端に推し進めていくと人工的に雲を発生させて温暖化を防止することや、遺伝子レベルで自然に介入することも可能です。農作物に被害を与える害虫や、病気を伝染させる蚊が発生しないように、遺伝子を組み変えてしまう。実際に応用した例では蚊を減少させた結果、別の害虫が発生したということです。人間が自然を再創造することによって、またしっぺ返しが来る。危機的な状況を自分たちでつくってしまっているわけです。

篠原:そこにも、アーレントのいう、人間の条件を人為的に構築し、維持存続させるというロジックがあるのかもしれません。1950年代の著作の段階ですでに、アーレントは人間の条件の人為性に関して、試験管ベビーや原子力を例にして論じていました。リジェネラティブといっても、自然へのコントロール力を上げるというだけであって、人為の領域を拡張しているだけだという観点から、捉え直すことができるかもしれませんね。やはり、人為のリミットの先にあるものとしての自然と向き合うという態度が大事なのではないでしょうか。
能作:菌のような弱い力というのは、リジェネラティブという強い力との対比から考えました。例えば里山は、人間が弱い力で介入することで環境が保全されています。それぐらいの弱い力で建築をつくれないかというのが、私たちが考えているアプローチです。伝統構法に見られる石場建ても、小さなフットプリントで、生分解性の材料でつくることにより、弱い力で建築を建てる方法の一つです。
篠原:土中環境を考えるのは、微生物が住み着く領域に目を向け、微生物から学ぶということだけど、他方で、空き家が増えていくとか(最近聞いた話だと、小豆島の空き家率は26%)、商店街が衰退するとか、人間がこれまでつくった人為的構築物そのものが使われなくなり、放擲(ほうてき)されていくという現実がある。放擲される状況においては、雑草が生えてきたりして、要は再び自然化されていくわけで、そうなると、人為の領域を自然から切り離すという近代的な人間の条件に関する想定そのものが成り立たなくなるのでしょうが、その状況で人間がこれからも生きていくことの条件を考えるとしたら、どう考えたらいいのか。僕は最近ずっとこういうことばかり考えているのだけれど、建築に関わる皆さんにも、この現実に対する応答のようなことを求めたいと考えます。建築の専門家ではないという身勝手な立場からの注文で恐縮ですが、建築空間としての新しさみたいなことがそのような状況においてありうるのかどうかという問いなのですが、もしかしたら、僕が提起する問いは、能作さん、常山さんの土中環境への着目とは、ズレてしまっているのかもしれない。それはともかくとして、皆さんは、建築が成り立つ条件を考え直しているところだと思うけれども、そこにでき上がる建築の形ということにまで意識が向かっているのだろうか。例えば木という素材に着目するのはいいとして、土中環境を意識した場合、これがどういう形になっていくのか。人為的に世界を構築することを前提とした思想への反省からの建築ということが、考えられているのかどうか。
能作:具体的にはどのようなことでしょうか。
篠原:というのも、このあいだ11月に、ベルリンの展覧会(Akademie der Künsteで開催された「The Great Repair」展)に友人と行ったら、「西大井のあな」の展示があって、模型もあり、写真もあったのですが、彼女から「こういうのは東ベルリンにはいっぱいある」と言われたんですよ。放置された建物にパンクスの連中が住み着いて、中はグラフィティだらけというのは普通にあるし、そのようなところでのDIYの実践もたくさんあるというのです。そのような普通のDIY実践の産物と「西大井のあな」を区別する境目はあるのかどうか。
常山:展示のテキストに「土を嗅ぎ、風を読み、日を感じて」と書きました。当たり前のことですが、実際の空間では、美しい、気持ちいいと感じるのは、視覚でとらえた形だけでなく、空気の質、光の入り方、匂いなどを総合的に身体で知覚しています。私自身は、実際に毎日使う空間を自分の手で材料を加工してつくることで、空間を形だけではなく精度高く捉えることができるようになってきました。そうやって生態系を捉えることによって、雨から壁を守り、湿気を逃す建築の知恵が民家には反映されています。その失った感性を私たちは「野生」と呼んでいます。
篠原:なるほど。
常山:土中環境に意識がいくようになってから、合板を使いたくなくなりました。我々は改修で出た小さな木屑は庭のコンポストに捨てているのですが、無垢材はあっという間に姿を消す一方で、糊で固められた合板は分解されずそのまま残っています。土に還らないんです。そうすると合板という材料がなんだか気持ち悪いものに感じられてきて、合板で仕上げられた空間も美しいと思えなくなりました。知識が増えることで感性が変わり、空間の認識も形だけではないものになってきたというのが実感です。ルイス・カーンが設計した建物に行くと、清々しく気持ちよいのです。それは雨水が綺麗に流れる窓回りの水切りだったり、谷間に流れる小川の湿気が風と一緒に流れる配置計画であったり、素材と周辺環境の特性をものすごい感度で捉えた形として設計されているからと感じました。
篠原:そうでしょうね。写真には形しか写らないから、写真だけで理解してもらうのは難しい。実際に行って手で触れて直接的に経験しないとわからない。ただそれは逆に言うと、直接的な経験のシェアがないところでは理解できない、ということでもある。つまり、筋道立てた思想的精緻化・理論化にまでは至っていない。
常山:この展覧会では、なるべく素材やつくり方を見せるようにしています。普段自分たちが建築をつくるときと同じように、土に還るもので、地球に負荷が少ないように、ゴミにならないものを使っていくことで、それで気持ちいいと感じられるようにつくる、そこにこだわりました。もちろん形も好きなんです、建築をやっているから。でもそれは語って議論するものではなく、自分の中で大事にしていくものであるような気がします。
能作:人類学者のティム・インゴルドの著作『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』によれば、形と素材の関係についてギリシア哲学以来、つくり手が心の中に描いた形を素材に押しつけるプロセスとして捉えられていました。しかし、インゴルドは素材を起点に成長していくものとして形を捉えています。建築の場合は、素材を起点にして構法を考えていくというプロセスとして私は考えています。また構法というのは生産システムも含んでおり、資源と建築とのつながり、廃棄物の扱いとも関係しています。生産から廃棄まで、システム全体がうまくいくような形を考えます。より広範囲に形の問題、あるいはシステムの問題が考えられるようになってきました。
能作:菌のような弱い力というのは、リジェネラティブという強い力との対比から考えました。例えば里山は、人間が弱い力で介入することで環境が保全されています。それぐらいの弱い力で建築をつくれないかというのが、私たちが考えているアプローチです。伝統構法に見られる石場建ても、小さなフットプリントで、生分解性の材料でつくることにより、弱い力で建築を建てる方法の一つです。
篠原:土中環境を考えるのは、微生物が住み着く領域に目を向け、微生物から学ぶということだけど、他方で、空き家が増えていくとか(最近聞いた話だと、小豆島の空き家率は26%)、商店街が衰退するとか、人間がこれまでつくった人為的構築物そのものが使われなくなり、放擲(ほうてき)されていくという現実がある。放擲される状況においては、雑草が生えてきたりして、要は再び自然化されていくわけで、そうなると、人為の領域を自然から切り離すという近代的な人間の条件に関する想定そのものが成り立たなくなるのでしょうが、その状況で人間がこれからも生きていくことの条件を考えるとしたら、どう考えたらいいのか。僕は最近ずっとこういうことばかり考えているのだけれど、建築に関わる皆さんにも、この現実に対する応答のようなことを求めたいと考えます。建築の専門家ではないという身勝手な立場からの注文で恐縮ですが、建築空間としての新しさみたいなことがそのような状況においてありうるのかどうかという問いなのですが、もしかしたら、僕が提起する問いは、能作さん、常山さんの土中環境への着目とは、ズレてしまっているのかもしれない。それはともかくとして、皆さんは、建築が成り立つ条件を考え直しているところだと思うけれども、そこにでき上がる建築の形ということにまで意識が向かっているのだろうか。例えば木という素材に着目するのはいいとして、土中環境を意識した場合、これがどういう形になっていくのか。人為的に世界を構築することを前提とした思想への反省からの建築ということが、考えられているのかどうか。
能作:具体的にはどのようなことでしょうか。
篠原:というのも、このあいだ11月に、ベルリンの展覧会(Akademie der Künsteで開催された「The Great Repair」展)に友人と行ったら、「西大井のあな」の展示があって、模型もあり、写真もあったのですが、彼女から「こういうのは東ベルリンにはいっぱいある」と言われたんですよ。放置された建物にパンクスの連中が住み着いて、中はグラフィティだらけというのは普通にあるし、そのようなところでのDIYの実践もたくさんあるというのです。そのような普通のDIY実践の産物と「西大井のあな」を区別する境目はあるのかどうか。
常山:展示のテキストに「土を嗅ぎ、風を読み、日を感じて」と書きました。当たり前のことですが、実際の空間では、美しい、気持ちいいと感じるのは、視覚でとらえた形だけでなく、空気の質、光の入り方、匂いなどを総合的に身体で知覚しています。私自身は、実際に毎日使う空間を自分の手で材料を加工してつくることで、空間を形だけではなく精度高く捉えることができるようになってきました。そうやって生態系を捉えることによって、雨から壁を守り、湿気を逃す建築の知恵が民家には反映されています。その失った感性を私たちは「野生」と呼んでいます。
篠原:なるほど。
常山:土中環境に意識がいくようになってから、合板を使いたくなくなりました。我々は改修で出た小さな木屑は庭のコンポストに捨てているのですが、無垢材はあっという間に姿を消す一方で、糊で固められた合板は分解されずそのまま残っています。土に還らないんです。そうすると合板という材料がなんだか気持ち悪いものに感じられてきて、合板で仕上げられた空間も美しいと思えなくなりました。知識が増えることで感性が変わり、空間の認識も形だけではないものになってきたというのが実感です。ルイス・カーンが設計した建物に行くと、清々しく気持ちよいのです。それは雨水が綺麗に流れる窓回りの水切りだったり、谷間に流れる小川の湿気が風と一緒に流れる配置計画であったり、素材と周辺環境の特性をものすごい感度で捉えた形として設計されているからと感じました。
篠原:そうでしょうね。写真には形しか写らないから、写真だけで理解してもらうのは難しい。実際に行って手で触れて直接的に経験しないとわからない。ただそれは逆に言うと、直接的な経験のシェアがないところでは理解できない、ということでもある。つまり、筋道立てた思想的精緻化・理論化にまでは至っていない。
常山:この展覧会では、なるべく素材やつくり方を見せるようにしています。普段自分たちが建築をつくるときと同じように、土に還るもので、地球に負荷が少ないように、ゴミにならないものを使っていくことで、それで気持ちいいと感じられるようにつくる、そこにこだわりました。もちろん形も好きなんです、建築をやっているから。でもそれは語って議論するものではなく、自分の中で大事にしていくものであるような気がします。
能作:人類学者のティム・インゴルドの著作『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』によれば、形と素材の関係についてギリシア哲学以来、つくり手が心の中に描いた形を素材に押しつけるプロセスとして捉えられていました。しかし、インゴルドは素材を起点に成長していくものとして形を捉えています。建築の場合は、素材を起点にして構法を考えていくというプロセスとして私は考えています。また構法というのは生産システムも含んでおり、資源と建築とのつながり、廃棄物の扱いとも関係しています。生産から廃棄まで、システム全体がうまくいくような形を考えます。より広範囲に形の問題、あるいはシステムの問題が考えられるようになってきました。
ハビタブルな環境をつくるには
篠原:また身勝手な言い方で申し訳ないのですが、能作さんたちはヨーロッパ近代の建築家像に由来する、アーキテクトのステレオタイプに収まらないようなことをやろうとしているのですかね。「新しい空間のプロトタイプを発案し、現実に出現させて多くの人たちをビビらせてやるぞ!」、みたいな。そうだとしたら、そのときに、建築家の役割とはどういうものになりますか。建築家のデザインというものが、果たしてどういう意味をもつのか。
能作:これまでは物質循環をあまり考えずに、既製品の建材を選んで組み合わせたり、木造だったら在来工法というシステムに従ってつくったり、というようにあまり意識化してこなかった。だからデザインといっても狭い意味での形に行かざるを得なかったんですけど、今は資源と廃棄物との関係をつなぐ建築構法をデザインの領域として捉えています。
常山:ヨーロッパでも、そういう動きが見られます。解体現場で建築資材をもらってきて、それをカタログ化して売っている建築家がいたり。
篠原:こんなこと言うと反動的に聞こえるかもしれないけど、やはりアートとしての建築という意識があるのか、あるいはもはやアートなんか知らないぜ、というふうになってしまうのか、その辺がわからなくて。
能作:アートとして、というのはどういう意味でしょうか。
篠原:とてもベタにいうと、直島の「地中美術館」みたいな建築ですかね。光の実在感を、建築を通じて感じ取ることができる、と言いますか。あとは「金沢21世紀美術館」も、内外の境界線の不分明化といった空間経験が可能になると言われています。たとえばヴェネチア・ビエンナーレには、アート作品としての建築を見に来る人たちもいるのでしょうが、建築ならではの何かを信じている人は、それなりにいると思います。僕自身は、最初に話したような、人為とその限界をめぐる抽象的思考から出てくる建築のようなものがあるのだとしたら面白いのか、とか考えています。
能作:私の中ではアートとしての建築を考える場合、一つはこれまでの建築の歴史との参照関係として、もう一つは古典的なスケールとプロポーションの問題として捉えています。私はロバート・ヴェンチューリの凡庸さの議論がとても好きです。例えば「明野の高床」は、「独立基礎は面白いけど、上は普通だね」と言われたりするのですが、住宅の基礎といういかにも凡庸なものが新規的であり、建築家の表現の対象である上物が逆に凡庸であるということは、「明野の高床」のレトリックの一つです。インスタ映え的なものではなく、凡庸さを利用した表現をいつも潜ませています。
常山:「秋谷の木組」も軽やかさを出しつつ、コンクリート基礎の形が特別だったり。
能作:「秋谷の木組」の基礎の形は、篠原一男の「上原通りの住宅」で三又になっているコンクリートの構造を意識しました。あまり声高には言わないのですが。そういった過去の建築の参照をささやかに行なったりもしています。
常山:コンクリート量を減らすための形状でもあります。
篠原:なるほど。でもそういうことはもっと今回の展示で主張してもいいんじゃないかな。それは意識して出さないようにしているんですか。
常山:言葉ではなくて、模型と図面で感じ取ってほしいんです。建築を専門にしている方であれば、既存の基礎の形を知っているので、何か変だとは思うはずです。
能作:アートや哲学もいろいろな過去の文脈を編み込んでいるけれども、それを自分自身で解説することはあまりしてこなかったですね。
常山:言うとダサいと思ってしまう。
篠原:いや、言った方がいいかもしれない(笑)。専門家以外の人間には、過去の文脈とかわからないので、伝わらない。
能作:これまでは物質循環をあまり考えずに、既製品の建材を選んで組み合わせたり、木造だったら在来工法というシステムに従ってつくったり、というようにあまり意識化してこなかった。だからデザインといっても狭い意味での形に行かざるを得なかったんですけど、今は資源と廃棄物との関係をつなぐ建築構法をデザインの領域として捉えています。
常山:ヨーロッパでも、そういう動きが見られます。解体現場で建築資材をもらってきて、それをカタログ化して売っている建築家がいたり。
篠原:こんなこと言うと反動的に聞こえるかもしれないけど、やはりアートとしての建築という意識があるのか、あるいはもはやアートなんか知らないぜ、というふうになってしまうのか、その辺がわからなくて。
能作:アートとして、というのはどういう意味でしょうか。
篠原:とてもベタにいうと、直島の「地中美術館」みたいな建築ですかね。光の実在感を、建築を通じて感じ取ることができる、と言いますか。あとは「金沢21世紀美術館」も、内外の境界線の不分明化といった空間経験が可能になると言われています。たとえばヴェネチア・ビエンナーレには、アート作品としての建築を見に来る人たちもいるのでしょうが、建築ならではの何かを信じている人は、それなりにいると思います。僕自身は、最初に話したような、人為とその限界をめぐる抽象的思考から出てくる建築のようなものがあるのだとしたら面白いのか、とか考えています。
能作:私の中ではアートとしての建築を考える場合、一つはこれまでの建築の歴史との参照関係として、もう一つは古典的なスケールとプロポーションの問題として捉えています。私はロバート・ヴェンチューリの凡庸さの議論がとても好きです。例えば「明野の高床」は、「独立基礎は面白いけど、上は普通だね」と言われたりするのですが、住宅の基礎といういかにも凡庸なものが新規的であり、建築家の表現の対象である上物が逆に凡庸であるということは、「明野の高床」のレトリックの一つです。インスタ映え的なものではなく、凡庸さを利用した表現をいつも潜ませています。
常山:「秋谷の木組」も軽やかさを出しつつ、コンクリート基礎の形が特別だったり。
能作:「秋谷の木組」の基礎の形は、篠原一男の「上原通りの住宅」で三又になっているコンクリートの構造を意識しました。あまり声高には言わないのですが。そういった過去の建築の参照をささやかに行なったりもしています。
常山:コンクリート量を減らすための形状でもあります。
篠原:なるほど。でもそういうことはもっと今回の展示で主張してもいいんじゃないかな。それは意識して出さないようにしているんですか。
常山:言葉ではなくて、模型と図面で感じ取ってほしいんです。建築を専門にしている方であれば、既存の基礎の形を知っているので、何か変だとは思うはずです。
能作:アートや哲学もいろいろな過去の文脈を編み込んでいるけれども、それを自分自身で解説することはあまりしてこなかったですね。
常山:言うとダサいと思ってしまう。
篠原:いや、言った方がいいかもしれない(笑)。専門家以外の人間には、過去の文脈とかわからないので、伝わらない。

篠原:ただ、あえて一ついうと、能作さん、常山さんの建築には、流体的なものへの関心がうかがえます。流体的というのは、一時的に形として定まってはいるけど、変化の可能性を含みながら成り立っているということで、だから解体中だけれど、それは建設でもあるという動きのなかにある。これを映像作品で示すとかしたらいいのかもしれません。また、それがもっと面的に広がっていくと面白いのかなと思います。自宅の内部だけでなく、その周辺環境も、解体され、新しくなるという運動性が、自宅を拠点に発生したら面白い。ベルリンで見た謎の空き地でも、古屋とかキッチンとかトイレとかがそういう面的な領域内で連鎖的に起きていたのですが、そういうことは日本の都心では難しいだろうけれど、アーティストとかと協働したら何かできないですかね?お二人の中ではこれまでやってきたことが全部つながっているんでしょうけど、現実の場所としては、それぞれがまだバラバラに離れて建っている。これが一つの街区にいくつかの建物が複数あって、それらが互いに流体的な関係において成り立つみたいなのが発生するといいのでしょうが。
能作:物質循環への意識は、近隣の環境とは異なった関係性に関してだと思います。
隣接性については、私たちより上の世代のアトリエ・ワンや千葉学さんが、都心回帰の現象が起きたときに、隣の敷地との関係性にフォーカスを当てていました。1990年代の後半から2000年代ぐらいです。敷地の近傍を含めて建築のデザインを考えるという姿勢が出てきました。私たちが意識してるのは生産から廃棄を含めてのことなので、遠方から来る物質というものを、どうデザインするかということがテーマになっています。近傍のデザインとは違う、別のつながりをデザインし始めたのが私たちなのかな。逆に言うと、遠いところに目を向けすぎて、近傍が少しないがしろになっているかもしれません。
篠原:やはりまだ孤立しているんですよね。一つひとつで完結している印象がなくもない。
常山:まちづくりやコミュニティというテーマからは距離を置いてしまっています。私たちの実践に足りないのは、人やまちとのつながりかもしれないです。ただ、以前の集落の形成には地形との大きな関わりがあります。現代ではまちは建物などの人工物で覆われていますが、昔は水害に強く水が沸く、台地の縁に人々の生活圏があった。そういった今は目に見えなくなった土地や生態系と建築を再び接続させることに興味があるのかもしれません。そこから関東平野に接する山から直接木材を仕入れる伝統構法の大工さんや、弱い力で土中改善を行う造園家さんとはつながりが深くなる一方で、直接的なまちやまちの人と我々の実践との関係性はまだ整理できていません。
篠原:ただ、今回の展覧会では、人工物と自然の関係のジレンマという課題の難しさと向き合っているのだろうな、ということはわかります。人間が生きる条件というものがどういう論理で成り立つかということを、事物の水準において考え直すきっかけにはなります。人新世的な状況において、人工物を自然から切り離して完結させるというロジックそのものを問い直すことが求められます。違うロジックとは何だろう。すぐにわかるわけはないんですけど、それを考えるためのきっかけになる展示だったと思います。
能作:建築することが既に自然破壊であるという人もいますけど、例えば里山は人間が介入することで、相互的関係になっているわけで、一つのヒントになると捉えています。
篠原:どうなんだろう、建築は自然破壊なのはそうかもしれないけれど、とりわけ近代化以後の世界では、人間の行うことすべてが自然破壊といえるのでしょうが、自然破壊は人間世界の構築で、アスファルト、コンクリートでつくった人為の世界の拡張でもある。その拡張していく人為の世界が絶対的に成り立つかどうか、もしかしたら、壊れてしまうのではないかと考えると、破壊された自然のほうが今度は人間を破壊するかもしれない。というか、自然はそんなに弱いのか?地震や津波は、自然なるものは容易には壊れず、むしろ、自然から切り離されうるという想定そのものの誤りを突きつけているだけかもしれない。
能作:極論として、地球にとって人間が悪いんだから、人間の数を減すという考え方がありますね。
篠原:現実問題として少子化で人口は減っていくわけですよ。人口がピークのときに、負荷をかける形で営まれた生活は、もう現実問題として崩壊しつつあります。自然破壊とかは既に人間がやってしまったことで、今や自然は人間に理解不能な脅威として現れているのです。その不可解な状況の中でどうするのか。罪悪感みたいなものには、あまりとらわれる必要はない。いや、ないとは言わないけど、それよりも別の方向で考えた方がいいんじゃないかと思っています。
能作:罪悪感とは違う、別の意識とは何でしょう。ポジティブですか?
篠原:畏怖の念(reverence)をもつという感じかな。人間が生存していけるのかどうか、ということに対する恐れです。ディペシュ・チャクラバルティが言っているハビタビリティ(生存可能性)で問われるのは、人間を含めた諸々の存在者が生きていける場をつくるにはどうしたらいいのか、ということです。お互い傷つけないようにという消極的な態度から、人間が多くの人たち、多くの存在者と共存していけるような環境をどうやってつくれるのか、という方向。能作さんたちがやってることも、その観点からとらえ直せるように思います。
常山:日本は人口が減少していますが、世界的に見ればまだまだ増えていますし、世界中の人が日本人みたいに生活したら、地球資源が危機的状況になるのは間違いありません。それに対して今考えつく行動すべきことは、まずは都市で暮らす我々が今まで田舎や外国に頼っていた生産と分解を、都市で少しでもまかなっていくことです。その考えは後から間違っているとわかるかもしれないけれど。
篠原:間違ってると言われることはないと思うけど。
常山:間違っていたと後から自分で気付くかもしれない。我々は「西大井のあな」で自分たちの快適性の向上と、エネルギー消費の軽減を目的に断熱を行ったのですが、当初は数値だけを頼りに断熱性能の高い石油系材料を使っていました。そのうち生産時に出るCO2や廃棄物の問題を知るようになり、材料を数値だけで捉えるのではなく、総合的に評価し、国産の生分解性の断熱材を使用するようになりました。でもただ正解を待つ暇はないので、間違いを恐れずに、小さいことからやっていこうと思っています。
能作:物質循環への意識は、近隣の環境とは異なった関係性に関してだと思います。
隣接性については、私たちより上の世代のアトリエ・ワンや千葉学さんが、都心回帰の現象が起きたときに、隣の敷地との関係性にフォーカスを当てていました。1990年代の後半から2000年代ぐらいです。敷地の近傍を含めて建築のデザインを考えるという姿勢が出てきました。私たちが意識してるのは生産から廃棄を含めてのことなので、遠方から来る物質というものを、どうデザインするかということがテーマになっています。近傍のデザインとは違う、別のつながりをデザインし始めたのが私たちなのかな。逆に言うと、遠いところに目を向けすぎて、近傍が少しないがしろになっているかもしれません。
篠原:やはりまだ孤立しているんですよね。一つひとつで完結している印象がなくもない。
常山:まちづくりやコミュニティというテーマからは距離を置いてしまっています。私たちの実践に足りないのは、人やまちとのつながりかもしれないです。ただ、以前の集落の形成には地形との大きな関わりがあります。現代ではまちは建物などの人工物で覆われていますが、昔は水害に強く水が沸く、台地の縁に人々の生活圏があった。そういった今は目に見えなくなった土地や生態系と建築を再び接続させることに興味があるのかもしれません。そこから関東平野に接する山から直接木材を仕入れる伝統構法の大工さんや、弱い力で土中改善を行う造園家さんとはつながりが深くなる一方で、直接的なまちやまちの人と我々の実践との関係性はまだ整理できていません。
篠原:ただ、今回の展覧会では、人工物と自然の関係のジレンマという課題の難しさと向き合っているのだろうな、ということはわかります。人間が生きる条件というものがどういう論理で成り立つかということを、事物の水準において考え直すきっかけにはなります。人新世的な状況において、人工物を自然から切り離して完結させるというロジックそのものを問い直すことが求められます。違うロジックとは何だろう。すぐにわかるわけはないんですけど、それを考えるためのきっかけになる展示だったと思います。
能作:建築することが既に自然破壊であるという人もいますけど、例えば里山は人間が介入することで、相互的関係になっているわけで、一つのヒントになると捉えています。
篠原:どうなんだろう、建築は自然破壊なのはそうかもしれないけれど、とりわけ近代化以後の世界では、人間の行うことすべてが自然破壊といえるのでしょうが、自然破壊は人間世界の構築で、アスファルト、コンクリートでつくった人為の世界の拡張でもある。その拡張していく人為の世界が絶対的に成り立つかどうか、もしかしたら、壊れてしまうのではないかと考えると、破壊された自然のほうが今度は人間を破壊するかもしれない。というか、自然はそんなに弱いのか?地震や津波は、自然なるものは容易には壊れず、むしろ、自然から切り離されうるという想定そのものの誤りを突きつけているだけかもしれない。
能作:極論として、地球にとって人間が悪いんだから、人間の数を減すという考え方がありますね。
篠原:現実問題として少子化で人口は減っていくわけですよ。人口がピークのときに、負荷をかける形で営まれた生活は、もう現実問題として崩壊しつつあります。自然破壊とかは既に人間がやってしまったことで、今や自然は人間に理解不能な脅威として現れているのです。その不可解な状況の中でどうするのか。罪悪感みたいなものには、あまりとらわれる必要はない。いや、ないとは言わないけど、それよりも別の方向で考えた方がいいんじゃないかと思っています。
能作:罪悪感とは違う、別の意識とは何でしょう。ポジティブですか?
篠原:畏怖の念(reverence)をもつという感じかな。人間が生存していけるのかどうか、ということに対する恐れです。ディペシュ・チャクラバルティが言っているハビタビリティ(生存可能性)で問われるのは、人間を含めた諸々の存在者が生きていける場をつくるにはどうしたらいいのか、ということです。お互い傷つけないようにという消極的な態度から、人間が多くの人たち、多くの存在者と共存していけるような環境をどうやってつくれるのか、という方向。能作さんたちがやってることも、その観点からとらえ直せるように思います。
常山:日本は人口が減少していますが、世界的に見ればまだまだ増えていますし、世界中の人が日本人みたいに生活したら、地球資源が危機的状況になるのは間違いありません。それに対して今考えつく行動すべきことは、まずは都市で暮らす我々が今まで田舎や外国に頼っていた生産と分解を、都市で少しでもまかなっていくことです。その考えは後から間違っているとわかるかもしれないけれど。
篠原:間違ってると言われることはないと思うけど。
常山:間違っていたと後から自分で気付くかもしれない。我々は「西大井のあな」で自分たちの快適性の向上と、エネルギー消費の軽減を目的に断熱を行ったのですが、当初は数値だけを頼りに断熱性能の高い石油系材料を使っていました。そのうち生産時に出るCO2や廃棄物の問題を知るようになり、材料を数値だけで捉えるのではなく、総合的に評価し、国産の生分解性の断熱材を使用するようになりました。でもただ正解を待つ暇はないので、間違いを恐れずに、小さいことからやっていこうと思っています。

篠原:なるほどね。
常山:「西大井のあな」では、自分たちの住む環境をよくしたいというのがまずあって、その際に地球に負荷をかけていくことは自分たちの気持ちよさには全然つながらないので、やはりそれは減らしていきたいと、そのバランスで何ができるかを模索しています。
篠原:それこそがハビタブルな何かをつくるということでしょうね。この展覧会は、ハビタビリティを、土とか水の流れとかの物質レベルにまで踏み込んで示そうとしています。大事なのは、ここで提起された「人為とその限界」という問題設定への問いが、さらに多くの人にも問われるようになるかどうか、でしょうね。後の世代から、2020年代前半にこういう転回点があったと振り返られるような、そんな展覧会になるといいですね。
常山:「西大井のあな」では、自分たちの住む環境をよくしたいというのがまずあって、その際に地球に負荷をかけていくことは自分たちの気持ちよさには全然つながらないので、やはりそれは減らしていきたいと、そのバランスで何ができるかを模索しています。
篠原:それこそがハビタブルな何かをつくるということでしょうね。この展覧会は、ハビタビリティを、土とか水の流れとかの物質レベルにまで踏み込んで示そうとしています。大事なのは、ここで提起された「人為とその限界」という問題設定への問いが、さらに多くの人にも問われるようになるかどうか、でしょうね。後の世代から、2020年代前半にこういう転回点があったと振り返られるような、そんな展覧会になるといいですね。

篠原雅武(しのはらまさたけ)
1975年生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。哲学、環境人文学。現在、京都大学大学院総合生存学館(思修館)特定准教授。著書に『公共空間の政治理論』『⼈新世の哲学』(いずれも⼈⽂書院)、『空間のために』『全−⽣活論』『複数性のエコロ ジー』(いずれも以⽂社)、『⽣きられたニュータウン』(⻘⼟社)、『「⼈間以後」の哲学』(講談社選書メチエ)。訳書に『社会の新たな哲学』(マヌエル・デラ ンダ著、⼈⽂書院)、『⾃然なきエコロジー』(ティモシー・モートン著、以⽂社) などがある。

磯達雄 Tatsuo Iso
編集者・1988年名古屋大学卒業。1988~1999年日経アーキテクチュア編集部勤務後2000年独立。2002年~20年3月フリックスタジオ共同主宰。20年4月から宮沢洋とOffice Bungaを共同主宰。
https://bunganet.tokyo/
https://bunganet.tokyo/


Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。