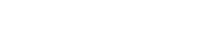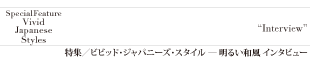
村野藤吾は生涯、ポストモダンをやりきった
——過去の様式の引用というと、いわゆるポストモダンの建築も連想します。
- 長谷川 ポストモダンの潮流が1970年代に始まりますが、「大阪新歌舞伎座」は58年ですから、村野藤吾をポストモダンの走りだととらえる人もいますね。ただ、僕に言わせれば70年代の動きとはなんの関係もないですよ。これまで話してきたとおり、村野さんはモダニズムの定式をすべてくずして生きているのだから、それをポストモダンだというのなら、彼は設計者として、最初から最後までポストモダンをやりきった人です。
——ポストモダンは一時代の潮流ではない、ということですね。
- 長谷川 そう。ポストモダンをひとつの流派みたいに考えて、そのポストモダンの建築はある時期にははやったけれど、またすぐにモダニズムが復活した、という言い方をされることがありますよね。あれは一種の徒花(あだばな)だった、と。ただ、僕はそうは考えない。ポストモダンの建築の本質というのは、建築の歴史はだるま落としみたいに、新しいものの上にさらに新しいものが積み重なってなりたっているのではない、ということなのだと思います。たとえば、ゴシックの後にルネサンスが出てきて、さらにその後にバロックが出てきて、というふうに歴史を学ぶけれど、実際の歴史はそういうものではない。ゴシックの誕生以来、そのままずっと続いてきて、21世紀の現在まで、細々としているかもしれないけれど、続いているんです。ルネサンスも、バロックも。日本建築でも、書院造や数寄屋、あるいは民家などが、今でも生きているんです。つまり、今現在の歴史の断面を切り取れば、モダニズムが一番大きな径をもったチューブかもしれませんが、ほかにもゴシックや数寄屋のチューブも細々と残っています。歴史というのは、そういうチューブの束でなりたっている、ということを認識するのがポストモダンだと思います。モダニズムという大きな束で、この世界全体が覆われるなんて幻想だよ、という主張がポストモダンの考え方だと理解すると、それは今でも非常に意味をもっていることだし、おそらくそれは、村野藤吾が考えていた歴史観と同じなんじゃないか、と僕は思います。
——そうした村野藤吾の考え方は、現在の建築家も引き継げるものですね。
- 長谷川 僕自身も死にそうだから、あえて言いたいのですが(笑)、建築家が建築家としての主体性をもっともっと強めていってほしい、とすごく思います。村野藤吾は、時には時代の潮流に背を向けながら、自分自身の内部に湧いてくるイマジネーションを実現するため、和風をはじめ、いろいろなものを過去や未来から取り入れ、それを自分の内側で燃やしているようなエネルギーをもった人でした。だから村野さんのように、自分の内側をもっと外側に出してほしいのです。かつてヴァルター・グロピウスが丹下健三に、人間の尺度が大事だと言ったそうです。それは、いわゆるヒューマンスケールなどの寸法のことを言ったのではないと思っています。僕の解釈では、建築家が自分の内側から湧いてくるもの、つまり人間としての自分の尺度を設計に投げ込むことが大事だ、ということなのだと思います。
>> 「大阪新歌舞伎座」の解説
>> 「道後温泉本館」の解説