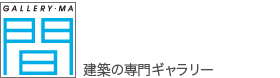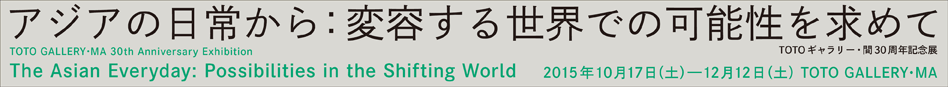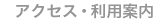- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO

しばらく中国で建築を勉強した身からすると、チャオ・ヤンは独特である。
中国で建築を学んだ若者の大半は、卒業後には「設計院」と呼ばれる国営由来の組織設計事務所に入所することを希望する。設計院が手がけるのは、中国の都市のそこかしこに見られる巨大な開発プロジェクト、そしてアイコニックな建築だ。彼らが中国の都市風景の基調をデザインしているのである。もちろん、設計院を好まない若者もいる。そうした若者はむしろ増えていると言えるだろう。そんな彼らがどこに向かうのかと言えば、建築家の主宰する小さなアトリエである。アトリエ建築家は大抵、欧米留学帰りだ。彼らは設計院主体の都市開発・都市風景には批判的であり、その間隙を縫うようにして、小規模な文化施設や商業施設を手がける。中国人建築家として初めてプリツカー賞を受賞したワン・シュウは、中国美術学院建築学院ディーンとして、手がけるプロジェクトの規模こそ大きいが、中国都市の現状を厳しく批判する点では、多くの中国人アトリエ建築家と色彩を同じくしている。
チャオ・ヤンが独特であるのは、都市部で衝突する「組織派」と「アトリエ派」のいずれにも当てはまらないからだ。アイコンをつくるのでもなく、アイコンを批判するのでもない。ただ、衝突の舞台であるところの「都市部」そのものから離脱し、雲南省の大理という、中国の広大な版図の周縁を活動拠点にしてしまった。
中国の「アトリエ派」は、設計院主体の都市開発を批判するため、往々にして、自然環境に親しい「田園的建築」をコンセプトに持ち出すのだが、チャオはその「田園」がよく残る周縁部で生活し、そこで営まれる日常から建築を立ち上げようとしている。その立ちふるまいは、中央の政治に疲れて田園へと逃避する中国伝統の厭世的文人のようであり、体制・反体制の政治闘争から離れて内省的に物語をつむぐ村上春樹的な「デタッチメント」のようでもある。いずれにしても言えるのは、チャオの実践はとても個性的で個人的なものである、ということだ。こうした個人的建築家であるチャオが、経済成長にともなって次々と現れた中国人若手建築家に先がけて、いち早く日本でプロジェクトを完成させ(「気仙沼大谷のみんなの家」)、TOTOギャラリー・間の展覧会で紹介されたことは興味深い。

「ニヤン川ビジターセンター」はチベットの村落部の川べりに建つ、小さな観光拠点施設である。チケットオフィスやトイレなど諸機能を内包する4つの不定形のボリュームが開放的な中庭を囲う構成だが、ともかく目を引くのがその色彩だ。石が積み上げられた各ボリュームの荒々しい壁面は、外側は真っ白に、そして中庭に面する内側は青や赤といった派手やかな原色に塗り分けられている。このように壁の各面を異なる色彩で塗り分ける意匠は、近隣にあるチベット仏教の寺院を見て思いついたものだという。その顔料は現地で採取されたものを使用しており、こうした現場主義は、建物の躯体に用いられた石と木と同様である。ただし、他方では、観光用に整備された道路を利用してクレーンを導入することで、近代的技術の届かない周縁の地で新たに大部材を用いることも試みている。ことほどさように、チャオの手さばきは、素朴な地域性を維持しつつ近代的な効率性や合理性も達成する、バランス感覚に優れた上手なものである。チャオは、このビジターセンターを、北京の建築家アトリエ「標準営造(standardarchitecture)」と協働で設計した。 続けて紹介されたのが、展覧会でも出展されている、雲南省大理市での2つのプロジェクトである。

もうひとつの大理プロジェクト「喜洲の住宅」(2015年)は、田園地帯にたつ豪邸(住み込みの家政婦の部屋も!)である。白色に塗られた壁面、外部への閉鎖性、大きな中庭の設置など、基本となるデザインは中国南方の伝統住居の翻案と言えるだろう。クライアントは重慶から大理に移住する若い芸術家夫妻であり、庭園部の設計などは彼らの意向がとくに強く反映されているのだという。クライアントがデザインの口出しをし、設計者(造園家)が指示を出して、職人が施工を仕上げていく、というプロセスは、まさに伝統的文人庭園の制作プロセスである。
そして最後に紹介されたのが、気仙沼の漁港の小さなコミュニティ施設「気仙沼大谷のみんなの家」(2013年)だ。妹島和世をアドバイザーに進行した、東日本大震災復興プロジェクト「みんなの家」のひとつである。雲南省大理から宮城県気仙沼港へ、言わば日中両国の周縁から周縁へ、チャオは繰り返し移動しては現地で住民とのミーティングをおこない、設計案もたびたび変更したという。変更のたびにつくり直されたスタディ用の白模型を説明するチャオのプレゼンテーションは、まるで日本の建築家である。そうして完成した最終案は、ガラス張りの個室や吹きさらしのベンチがトップライトの開けられたドーム空間を下支えする、開放的な構成のものとなった。このレクチャー翌日には久しぶりの再訪が計画されていたようで、チャオはそれが楽しみで仕方がないと言って、すべてのスライドをそっと終えた。

聴衆との質疑応答のなかで、チャオは、みずからを、周囲と戦う「ファイター」ではなく、むしろ協調していく「コラボレーター」だと位置づける一幕があった。チベットや大理で伝統的技術を継承する大工や石工、標準営造や妹島和世ら建築家、あるいは場所場所で千変万化なマテリアルやコンテクスト。あらゆる事物を複合的に考え、それらと格闘することなく自然な調停を目指しながら設計を進めるチャオの姿勢は、たしかにコラボレーターという言葉がよく似合う。
レクチャー後には、東北大学の本江正茂・石田壽一・五十嵐太郎各氏が壇上に上がって、チャオとのディスカッションもおこなわれた。日本と中国で許容される建築的ディテールの誤差の異なり、あるいは、辺境の地・大理における実践が建築のグローバルなトレンドに与える可能性などについて議論が交わされたのだが、とくに興味深かったのは、中国における「田園回帰」とも言うべき潮流の指摘である。チャオによれば、中国文化の核はそもそも田園地帯にあり、「改革開放」以後の急速な都市化中心主義のほうこそが異例である。そして、こうした「田園回帰」の考えは知識人や富裕層、投資家などに徐々に広まっているというのだ。「喜洲の住宅」のクライアントは、まさに、都市の喧騒や公害を嫌って田園地帯への移住を計画するインテリ富裕層である。
であるならば、田園へと流入するクライアントや資本を当て込んで、いずれはチャオのような非都市的建築家が増えてもおかしくはない。中国ではいま、経済成長が鈍化し、都市部でのプロジェクトが手に余るほどあった時代が過ぎ去りつつある。過渡期を迎えた中国において、「独特」と言うべきポジションにあったチャオは、あるいは新たな建築家のロールモデルになるのだろうか?

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。